2025-07-23
結婚を控えている皆さん、あるいは将来結婚を考えている皆さんにとって、経済的な不安は大きな悩みの一つではないでしょうか。
結婚式費用、新生活の準備費用…と、大きな出費が予想されます。
しかし、実は国から結婚を支援する制度があることをご存知でしょうか。
結婚を機に生活が変わることで、様々な経済的メリットを受けられる可能性があります。
この記事では、国が提供する結婚に関する経済的支援制度について、具体的に見ていきましょう。
知っておくことで、新生活をより安心してスタートさせることができるかもしれません。
結婚したらもらえるお金
結婚祝い金の支給額
結婚祝い金は、会社や親族などから支給されることが多いものです。
金額は、会社規模や支給する側の状況によって大きく異なります。
大企業では5万円~10万円、中小企業では3万円~5万円、アルバイト先では1万円~3万円程度が相場と言われています。
親族からの祝い金も、年齢や親密度によって金額が変動します。
友人からは3万円~5万円、兄弟姉妹からは5万円~10万円、親戚からは3万円~10万円程度が目安です。
結婚式に出席しない場合は、これらの金額から2万円程度差し引かれるケースもあります。
これらの金額はあくまでも目安であり、実際にはもっと多く、あるいは少なくなる可能性もあります。
結婚祝い金の申請方法
結婚祝い金の申請方法は、会社や団体によって異なります。
多くの場合、会社規定の申請フォーマットに必要事項を記入し、住民票などの書類を添付して提出します。
人事部や総務部といった部署に問い合わせ、手続き方法を確認しましょう。
所属している組合や共済会なども、結婚祝い金の支給制度を設けている場合がありますので、確認することをお勧めします。
結婚祝い金の対象者
結婚祝い金の対象者は、会社や団体によって異なりますが、一般的には、その会社や団体に所属する従業員や会員が結婚した場合が対象となります。
アルバイトやパートの方でも支給されるケースがありますので、就業規則や規定を確認してみましょう。
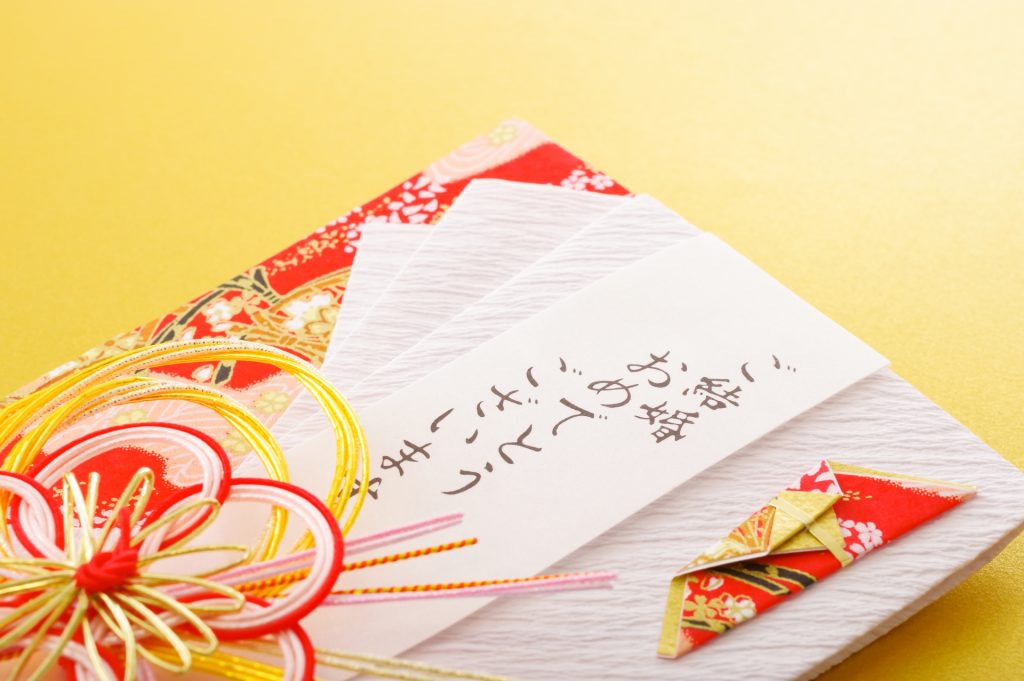
国からの結婚支援制度
制度の概要と目的
国レベルで結婚を直接支援する制度は、限られています。
最も代表的なものは、内閣府が少子化対策として実施している「結婚新生活支援事業」です。
これは、経済的な不安から結婚を躊躇する人を減らし、結婚・出産を促進することを目的としています。
受給資格の確認方法
結婚新生活支援事業の受給資格は、自治体によって異なりますが、一般的には以下の条件が挙げられます。
・夫婦ともに39歳以下であること
・世帯所得が500万円未満であること(奨学金の返済額は控除される場合があります)
・対象となる自治体に住民票があること
・婚姻届提出日における条件を満たしていること
具体的な条件や対象期間は、お住まいの自治体のホームページなどで確認する必要があります。
申請に必要な書類
申請に必要な書類も自治体によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。
・結婚助成金の申請書・誓約書
・結婚届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・世帯全員が記載されている住民票
・夫婦の前年中の所得証明書
・税金の滞納がないことを証明する書類
・新居に関する書類(契約書など)
・費用の支払いを証明する書類(領収書など)
事前に自治体窓口に問い合わせ、必要な書類を正確に確認しましょう。

結婚に関する国の経済支援
制度の比較と選択
国からの直接的な結婚支援制度は、前述の「結婚新生活支援事業」が中心です。
この事業は、新居の購入費用や賃貸費用、引っ越し費用などを支援するもので、最大60万円(自治体によって異なる)の補助が受けられる可能性があります。
しかし、年齢や所得制限など、受給条件が厳しいため、必ずしも全てのカップルが対象とは限りません。
相談窓口の情報
結婚に関する経済的な相談は、お住まいの自治体の窓口や、都道府県、国の機関などに相談することができます。
各機関のホームページや電話などで、相談窓口について確認しましょう。
必要に応じて、専門機関への相談も検討してみてください。
制度改正への対応
国の政策は常に変化します。
結婚に関する制度も例外ではありません。
最新の情報を常に確認し、制度の変更や新たな支援策の有無をチェックすることが大切です。
自治体のホームページや関係省庁のウェブサイトなどを活用し、最新の情報を入手しましょう。
まとめ
結婚は人生における大きな転換期であり、経済的な側面も重要な要素です。
この記事で紹介した結婚祝い金や、結婚新生活支援事業といった制度を活用することで、経済的な負担を軽減し、より安心して新生活をスタートさせることができるでしょう。
しかし、制度の内容や申請方法は自治体によって異なるため、お住まいの自治体で確認することが重要です。
また、制度は常に変化するため、最新の情報を確認し、必要に応じて専門機関に相談することも検討しましょう。
結婚を機に生活が変わることで、税金面や社会保険面でも様々なメリットが生まれる可能性もあります。
これらの制度を賢く活用し、幸せな結婚生活を送ってください。








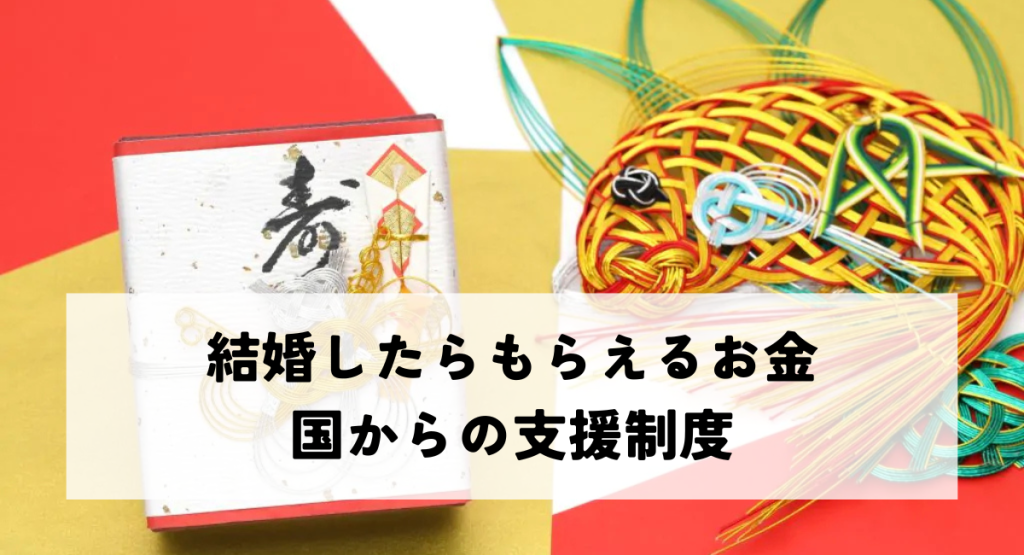



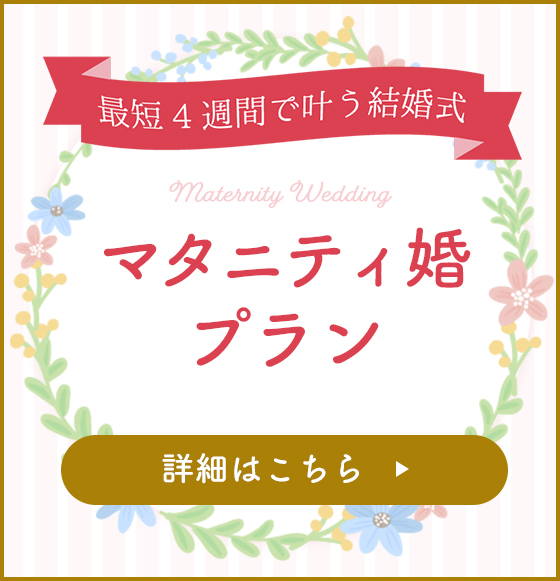

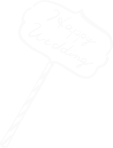



 ページTOP
ページTOP